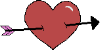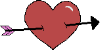|
|
|
|
今日からアドベントに入ります。先週の日曜日、みなさんで今年のクリスマスを迎えるための飾り付けをいたしました。玄関にはクリスマスツリー、エントランスには、イエスさまがお生まれになった家畜小屋のお人形セット(クリッペというそうですが・・・)、礼拝堂にはリース、四本のキャンドルを立てたクランツ、ポインセチア、そしてクリスマスの物語を描いた絵が飾られています。ほかの教会のことはあまり知りませんが、荒川教会はけっこう賑やかに飾るほうではないかと思います。
信仰的に言えば、こういう飾り付けをしなくてはいけない、ということではありません。教会は目に見えないものを大事にします。教会がアドベントに入って、こうした装いをする。それは、わたしたちの目を楽しませるだけではありません。わたしたちの信仰を、見えないものに向かって開かせるためのものであることを忘れないようにしたいと思います。
教会でクリスマスを迎えるのがはじめてという方もいらっしゃいますので、アドベントについてすこし説明しておきたいと思います。アドベントはイエスさまの降誕日(12月25日)の四つ前の日曜日から始まります。今日はその最初の日曜日で、聖壇に四本の蝋燭が立てられました。これをクランツといいまして、今日は一本だけ火を点しています。来週は二本、その次は三本と、火を点す数を増やしながら、一週一週、クリスマスが近づくのを数えるのです。
教会ではクランツを用いますが、お子さんのいる家庭ではアドベント・カレンダーを使って、クリスマスが来るのを数える、ということがあります。カレンダーの数字のところが扉になっていまして、開くとクリスマスにちなんだ聖書の言葉が書いてあったり、絵が描いてあったりするのです。アドベントのあいだ、それを一つずつ開いていって、クリスマスが近づくのを数えるという仕組みになっています。
いずれにせよ、アドベントは「待つ」ということが大事なのです。クランツとか、アドベントカレンダーというのは、待つということを教えるための道具なのです。
もっとも、アドベントという言葉に「待つ」という意味はありません。アドベントの意味は「やってくる」という意味です。何がやってくるのでしょうか。イエスさまです。神さまがわたしたちに贈ってくださった最高の贈り物である、イエスさまがわたしたちのもとに来て下さる、それを待つのです。それがアドベントです。
|
|
|
|
|
|
ひとくちに「待つ」と言っても、いろいろな「待つ」があります。たとえば、バス停でバスを待つ。時刻表にバスが来る時間が書いてありますが、あと15分、あと5分と、その時が来るのを待つのです。
そのぐらいは待つうちに入らないとおもうかもしれませんが、わたしの田舎では、日が暮れるとバス停は真っ暗になります。周りに家も、お店も、外灯もない、おまけにほとんど車が通らない。そんな真っ暗な寂しいところで、一時間に一本のバスを待つわけです。時間になれば来ることが分かっていても、そういうところでは1分が非常に長く感じます。たった15分待つにしても、ほんとうに来るのかしらんと心配になってくる。そんな不安を心に抱きながら待っています。真っ暗な道の遠くにバスのヘッドライトが小さな光として見えてくると、非常に安心します。
待つのがバスではなく、救急車だったらどうでしょうか。一分一秒でも早く来てほしい、と祈るような気持ちになるに違いありません。そのように、待つということには、不安とか、祈りが込められていることがあります。
合格通知を待つ、当選のお知らせを待つという時には、発表の日付というのがあるにしても、待っているのはその日が来ることではなく、結果を待つのです。どんな知らせが来るかわからないのですから、やはり、不安があり、そして良い返事が来るようにと祈るような気持ちがありましょう。
もっと長いスパンで待たなければならないものもあります。「ローマは一日にして成らず」とか、「万里の道も一歩から」という諺がありますように、大きな目標に向かって進むということは、小さな努力を長いあいだ積み重ねていかなければなりません。そのために必要なのは、この努力の先に自分が待っているものがあるのだという希望、そして忍耐です。待つということは、希望を持つことであり、忍耐することでもあると言えましょう。
それから、熟成させるためにも待つことが必要です。漬物とか、お酒とか、最近ではお肉や魚も熟成させるとうま味が出ると言われます。食べ物ではありませんが。アンティーク家具なども、時間を経て、新品とは違う味わいを楽しむことができます。長い時間をかけて出てくる味わいを待つ、そこにあるのは期待です。
話は変わりますが、NHKラジオで毎月一回放送されている「みんなでひきこもりラジオ」という番組があります。番組に寄せられたひきこもり当事者の声を、アナウンサーが紹介するというものです。寄せられる声は、ひとりひとり違うのですが、苦しい、何もできない、生きている意味がわからない、そんな悲鳴のような声なのですけれども、そこにあるのは絶望感だけではありません。これではいけないということを、痛いほどに感じている。自分を変えることができるならば、変えたいという切なる思いがそこにあるのです。
それを聞きながら、わたしは太宰治の「待つ」という短編を思い起こしました。片田舎で、毎日、家族のために家事をしている真面目な女性が、毎日、買い物帰りに駅に寄って、そこでしばらくの時間をすこで過ごすのです。どうして、そんなことをしているかというと、わたしは待っているのです、と女性はいいます。けれども、汽車を待っているのではない。ひとを待っているのでも、荷物を待っているのでもない。実は、何を待っているか、自分でもわからないのだ、ともいうのです。しかし、もしかしたら何か新しいことがあるのではないか。変わり映えのしない毎日を、死ぬまで続けるしかない自分を、何かが変えてくるのではないか、そういう出会い、訪れを微かに期待して、毎日、駅に行っているのだ、というのです。
そのように、何を待ったらいいのか分からなくても、自分を変えてくる何かの訪れを待ち続けている、そういう希望を失ったひとが希望の最後の一欠片として持っているような「待つ」もあるのです。
いろいろな「待つ」があります。どんな「待つ」でありましても、待つというのは、けっして人生において無駄な時間、余計な時間ではありません。待つということには、信じること、祈ること、忍耐すること、希望、希望を失ったときの最後のひとかけらの希望といった、生きていく上で非常に大切なものがあるのです。
ところが、最近は、携帯電話とか、24時間営業のコンビニエンスストアとか、ネット通販とか、いろいろなことが便利になりすぎて、待つということができない世の中になっています。それと同時に、信じること、祈ること、忍耐すること、希望ができない世の中になっているのではないでしょうか。
アドベントで大事なのは「待つ」ということです。クリスマスは、待ち望むということから始まるのです。ひとつは、イエスさまが来て下さったことを神さまに感謝して礼拝する日を待つ、ということです。もうひとつは、イエスさまが、わたしのこころに宿ってくださり、イエスさまが共にいてくださるという思いに満たされることを待つということです。三つ目は、イエスさまの再臨の日、主の日が来ることを待ち望むことです。そのような三つの意味で、わたしたちはイエスさまが来て下さることを待ち望むのです。その日が来ることを信じて、祈りをもって、忍耐をもって、希望をもって待ち望むのです。それがアドベントです。
|
|
|
|
|
|
さて、そのようなアドベントの最初の日曜日に、『マタイによる福音書』の冒頭の、イエスさまがお生まれになるまでの系図が書かれているところをお読みしました。
マタイは、なんでこんな長い系図を書かなければならなかったのでしょうか。しかも、初っ端にこれが書かれているのです。これから聖書を読み始めようと、期待を込めて聖書を開いてみますと、いきなり訳の分からない長い系図が書いてあって、読む気が失せたという話を、何度も聞かされました。
クリスチャンであっても旧約聖書に馴染みがないと、やはりこの系図は人の名前の羅列に過ぎない、味気ないものにしか見えないに違いありません。逆にいうと、イエスさまを知るためには、旧約聖書を読むということが、それだけ大事であるということなのです。読むのがたいへんでしたら、子ども向けの絵本でもいいから、旧約聖書に親しんでほしいと思います。
この系図は、アブラハムからダビデまで、ダビデからバビロン捕囚まで、バビロン捕囚からイエスさまの誕生まで、と三つに区切られています。この系図を知るためには、せめてアブラハム、ダビデ、バビロン捕囚について、旧約聖書がどんなことが書いているののか、そのことを学ぶ必要があるのです。それが分かってきますと、マタイが、イエスさまの誕生を語る時、この系図から書き始めた理由がわかってくるのです。
結論から申し上げましょう。1節にこう書かれています。
アブラハムの子ダビデの子、イエス・キリストの系図。
イエスさまはアブラハムの子であり、ダビデの子である。つまり、神さまがアブラハムになさった、「あなたの子孫を大いなる国民にし、すべてのひとの祝福の基にする」という約束、そしてダビデになさった「あなたの王座、あなたの王国をとこしえのものとする」という約束、この二つの約束を成就する方として、イエスさまはお生まれになったのだ、ということなのです。
言い換えれば、それは「イエスさまが約束のメシアである」ということです。それが、この系図が物語っているいちばん大事なことです。
|
|
|
|
|
系図とは歴史でもあります。この系図には、アブラハムからイエスさまの誕生まで続いた2000年の歴史があります。アブラハムに対する神さまの約束、ダビデに対する神さまの約束を受け継いできた歴史です。その2000年の歴史を担った中心人物の名がここに列挙されているのです。
しかし、必ずしも立派な人たちではありませんでした。胸をはって「自分たちこそ神の民の歴史を担ってきたのだ」と言えるひとたちではないのです。今日の説教題は、「イエスさまの汚れた系図」としました。ここに名を連ねている多くのひとびとが、人間の弱さ、不信仰、罪と恥で真っ黒なひとたちである、と言っていいのです。
それにもかかわらず、神さまはこの民を憐れんで、アブラハムになされた約束、ダビデになされた約束を守りぬかれます。すべては神さまの憐れみによることなのです。この系図が物語っている歴史は、神さまが憐れんで、奇跡的に繋いでくださった歴史なのです。神の民の歴史は、ひとびとの信仰と正しさ、強さと立派さによって担われてきたのではありませんでした。神さまの憐れみ深さと、約束なさったことを必ず果たされるという神さまの真実によって紡がれてきたものだった、ということです。そして、神さまの憐れみと真実の賜物としてイエスさまがお生まれになった、と語っているるのがこの系図です。
今日はそのすべてをお話しすることはできませんが、幾つか拾い挙げてみましょう。
3節、《ユダはタマルによってペレツとゼラを》とあります。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の子が生まれるのですが、その三男がユダです。そのユダのスキャンダルを明らかにしているのが、《ユダはタマルによってペレツとゼラを》という部分です。
どういうことかと言いますと、タマルというのはユダの妻ではありません。ユダの長男の妻なのです。ユダは自分の息子の妻とのあいだに、ベレツとゼラを生んだ、といわれているわけです。
なぜ、そんなことが起こったのか。創世記38章に書かれています。今日はその話をする時間はありませんが、たいへんおぞましいことが、正しくないことが起こっていることは確かなのです。それがユダ族の始まりであり、ダビデを輩出する部族となるのです。
次に5節をみます。《サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを》とあります。ラハブという女性は、異邦人の女性で、場末の娼婦でした。そういう社会の底辺で生きていた女性が、ユダヤ人のサルモンとの間に子を生みます。そしてボアズが生まれます。
そして、《ボアズはルツによってオベドを》とあります。ルツは、やはり異邦人の女性でした。ボアズがそのルツと結婚するまでの話が、旧約聖書の『ルツ記』に書かれています。たいへん美しい物語です。ルツは深い悲しみを負った女性でしたが、心美しく、働き者で、立派な女性でした。それがボアズの目に留まり、ボアズはルツと結婚します。そして、オベドが生まれ、オベドの子がエッサイで、エッサイの子どもがダビデです。ダビデが生まれるためには、『ルツ記』というひとつの書物になるぐらい、多くの神さまの愛と導きが介在していたのです。
|
|
| |
|
|
| |
6節後半には《ダビデはウリヤの妻によってソロモンをもうけ》とあります。ウリヤは、ダビデの家来、武将でした。その家来の妻によって、ソロモンが生まれた、というのです。先ほどのユダは自分の息子の妻によって子をもうけました。ダビデは自分の家来ウリヤの妻によって子をもうけました。マタイの系図は、こういうことを隠すのではなく、明らかにする系図です。
11〜12節に《ヨシヤは、バビロンへ移住させられたころ、エコンヤとその兄弟をもうけた。バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエルをもうけ》とあります。ヨシヤ王は、ダビデ王朝末期に現れた名君でした。エジプトとバビロンが覇権を争い、その二つの大国のあいだでイスラエルはどちらにつくかと揺れ動きます。ヨシヤ王はエジプトを頼らず、バビロンに媚びず、神さまだけを依り頼み、神さまの保護を受けることができたのでした。
しかし、ヨシヤ王の死後、ダビデ王朝はまっしぐらに滅亡に向かいます。詳細な話をすることはできませんが、22年間のあいだに四人の王が即位しました。そして、エジプトに敗れ、バビロンに敗れ、最後の王となったゼデキヤは、バビロンに連れ去られて、そこで死にます。ゼデキヤの息子たちもみな殺されてしまいます。こうして約五百年続いたダビデ王朝は完全に断絶してしまったかのように思えました。
ところが、バビロンに連れ去られたヨシヤ王の子エコンヤ(ヨヤキン)は、37年間の幽閉の後、ほんとうに不思議なことですが、突然、解放されます。バビロンの王が代替わりしますと、理由はわかりませんが、37年の幽閉から解き放たれ、バビロン王の友人として破格の待遇を受けるようになるのです。
エコンヤは申し分のない生活をして、バビロンで死にます。エコンヤは死ぬまで祖国に帰ることはできませんでしたが、そのあいだにシャルティエルという息子が生まれた、というのです。つまり、ダビデ王国は滅んでしまいましたが、首の皮一枚で、ダビデの血筋が奇蹟的に繋がっていたのです。
|
|
| |
|
|
| |
12節に《バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエル、シャルティエルはゼルバベルを》とあります。シャルティエルの子どもがゼルバベルです。ゼルバベルは、イスラエルの人たちがバビロンから解放されて祖国に帰ったときに、エルサレムの復興、神殿を再建する指導者となりました。
ゼルバベル以降に記されている人物については、聖書に記載がありません。イスラエルは、その後、ペルシア、ギリシア、そしてローマの支配下に入り、独立をうしないました。しかし、そのなかにあってもダビデの血筋は失われず、ヨセフまで続いたのです。
そして、イエスさまが生まれました。決して誇らしい歴史が綴られた系図ではありません。息子の妻とのあいだに子を産んだとか、家来の妻を奪って子を産んだとか、この系図が物語っているのは、神の民の優秀さとか、誇らしさではなく、その罪深さなのです。そして、それにも関わらず、憐れみが貫かれた歴史です。
17節にこう書かれています。
こうして、全部合わせると、アブラハムからダビデまで十四代、ダビデからバビロンへの移住まで十四代、バビロンへ移されてからキリストまでが十四代である。
十四代、十四代、十四代というのは、あまりにもできすぎのような気がします。実際は、そうなるようにマタイが系図を編集している可能性もあるでしょう。しかし、なぜ、そんなことをしたか。それは、この罪深い歴史にも拘わらず、神さまのご計画はすこしも迷いなく、狂いなく、アブラハムからずっと貫かれていたのだ、ということなのです。その神さまの真実と憐れみによって、イエスさまがわたしたちに与えられたのです。
みなさん、わたしたちも御自分の人生をふり返って見て下さい。わたしたちがイエスさまを知り、神さまの愛を知る者とされるために、どれほど多くの愛が注がれてきたか、そのことを思い起こしたいと思います。 |
|
 |
| 目次 |
|

|
|
| 聖書 新共同訳: |
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible
Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|