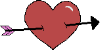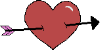|
|
|
|
明日、10月31日は宗教改革記念日です。ルターは、この『ローマの信徒への手紙』の研究をとおして「福音の再発見」をし、それが宗教改革の原動力となりました。
イエスさまがしてくださったこと、してくださること、この二つによってわたしたちが救われること、それが福音です。ルターの福音の再発見とは、この福音を『ローマの信徒への手紙』のなかに見いだしたことを言います。
みなさんは、「何を当たり前のことを言っているのか」と思うでしょう。しかし、ルターの時代の教会は違う考えを教えていました。救われるためにはイエスさまを信じているだけでは足りず、ひとりひとりが罪の償いをしなければならないと教えられていたのです。
どうやって罪を償えばいいのでしょうか。ひと言で言えば、善行や苦行をするのです。貧しい人への慈善、勤勉な生活、禁欲的な清貧の生活、教会への奉仕、献金、断食、徹夜祈祷などをして、それで足りない分は、死んでからも煉獄という場所に行って、自分が犯した罪を償うための苦しみが続くと言われていました。そして、すべてを償い終えてから、ようやく天国に入ることができるのです。それがルターの時代の教会の教えでした。
敬虔な修道士であったルターは、忠実にその教えに従う生活をしていました。すすんで慈善を行い、貞潔、従順、勤勉などの徳を積み、人一倍、断食、清貧、徹夜などの苦行を行いました。それでも、自分の罪を償うのには足りないのではないかと恐れ、不安に苛まされていたようです。
有名なルターの伝記には、彼が修道士をしていた頃の様子が、こう書かれています。
どんな善いわざにしろ、人がみずからを救うためにやれることは、これを実行しようと、ルターは決心したのである。
彼はときどき、三日間ぶっ通しに、パンひとかけらも食べずに断食した。断食の期間は、ごちそうの期間よりも彼を力づけた。受難節は復活節よりもなぐさめを与えたのだった。彼は徹夜と祈りとを、規則で定められている以上に、自分に課した。彼は許可されている毛布を脱ぎ捨てて、ほとんど死ぬほどからだをこごえさせた。時おり、彼は自分のきよらかさを誇って、こう言ったのである、「私はきょう何も悪いことをしなかった」と。そうすると、疑惑湧き起こってくるのであった。「おまえは十分に断食したのか。おまえはほんとうに貧乏なのか。」そこで彼は、体面上やむをえないもののほか、いっさいを剥ぎ取ったものだった。
ベイントン、『我ここに立つ』、聖文社、1962年、34頁
凄まじい生活です。ここまで徹底して、自分で自分を罰するような生活をしても、まだ罪の償いが成立しないとすれば、いったい誰が自分の犯した罪を償うことが出来るのでしょうか。
救いとは何でしょうか。聖書において「救い」とは、人生のさまざまな苦難から救われることだけを意味するのではありません。わたしたちの人生には、もっと深いところに、神さまに対する罪という大問題が横たわっています。それは、わたしたちが神さまの怒りと審きの対象であることを意味します。
たとえば、世の中には理不尽としか言えないようなことがあります。そういう時に、「神さまがいるならどうして」とか、「神も仏もあるものか」と、神さまに怒りをぶつける人がいるでしょう。自分が神さまに対してどんな生き方をしてきたのかを考える人は少ないのです。神さまへの礼儀も感謝もなく、自己中心、人間中心の生き方をしてきたのではないでしょうか。
それを考えたら、神さまに愛想を尽かされても仕方がありません。少なくとも神さまに文句を言ったり、当然のように神さまの愛や保護を受ける資格があるようには言えないのです。むしろ、災難に遭うとき、神さまの怒りや審きが自分に向けられているのだ、と考えるほうが自然なことではないでしょうか。
人間が神さまに対して罪びとであるとは、そういうことです。 そして、救いの問題とは、どうしたらこのような罪の問題が解決し、神さまに愛され、祝福される者になることができるのか、ということなのです。
それが、ルターが悩んだ救いの問題でした。ルターは先ほど紹介したような生活を送りながら、聖書研究に勤しみます。そして『ローマの信徒への手紙』を丹念に読むことによって、ひとは行いによってではなく、恵みによって救われるという福音に気づいたのです。それが福音の再発見です。
その時、ルターはいままで自分の苦しめていた内面の問題、自分を責め苛む神の怒りへの恐れ、その原因である罪との終わりなき戦いがすっかり消えてなくなり、まるでパラダイスに入ったように幸せ神さまの愛と平和で心が満たされたと言っています。
わたしはパウロのローマ人への手紙を理解したいと切望したし、別に障害となるものもなかったが、ただ『神の義』という表現につまずいた。なぜならわたしは、義を、それによって神は正しいのであるし、正しくない人間を罰するのに正しく処置したもうのである、という意味にとったからだ。(中略)
日夜わたしは思索し、ついにわたしは、神の義と、『信仰による義人は生きる』という言葉との関連を、見つけた。それからわたしは、神の義が、それによって御名と全くのあわれみから神が信仰を通してわれらを義としたもうところの正しさである、ということを理解した。そこでわたしは、自分が生まれ変わって、開いている戸口からパラダイスにはいったのを感じたのである。聖書全体が新しい意味を持つにいたった。以前には『神の義』がわあしを憎悪でいっぱいにしていたのに、今ではそれがわたしには、いっそう大きな愛のうちに、言いようもなく快いものになった。このパウロの一句は、私には天国へのとびらになったのである。
前掲書、63頁
「聖書全体が新しい意味を持つにいたった」と書かれています。わたしたちは最初から「信仰義認」を教えられて信仰に入りましたから、「福音の再発見」なんて大袈裟な言い方に聞こえるかもしれませんが、これは聖書全体に新しい意味を与え、クリスチャンの生き方を変え、教会に大変革をもたらすほどの大きな発見だったのです。
ですから、聖ペトロ大聖堂の修築のために「贖宥状(免罪符)」が売られたとき、ルターは黙っていることができませんでした。ハロウィーンの日(10月31日)に、「95箇条の提題」をヴィッテンベルク城教会の門扉に貼り、問題提起をしたのでした。これが宗教改革の発端です。
このように、ルターにとって、『ローマの信徒への手紙』は福音を再発見し、天国の扉が自分に開かれているのを見せてくれる書でした。聖書は『創世記』から『ヨハネの黙示録』にいたるまで等しく神の御言葉であり、読まなくていい書はひとつもありません。どの書も、わたしたちに人生の目的を教え、生きる力と希望を与える命のパンです。味の違いこそあれ、けっして優劣をつけるものではないのです。
それにも関わらず、これから私たちが読んでいく『ローマの信徒への手紙』は、聖書全巻のなかでとりわけ重要な書であると言われることが多いのも事実です。だれの言葉であったか忘れましたが、『ローマの信徒への手紙』は、聖書全体にキリストの血を行き巡らせる心臓のようなものだと言っているのを読んだことがあります。この書を読み、理解し、これに照らして聖書全体を読んだ時、はじめて聖書の神の愛と恵みの書であることが分かってくるというのです。
|
|
|
|
|
|
さて、これから『ローマの信徒への手紙』をご一緒に読んでいきます。
キリスト・イエスの僕、神の福音のために選び出され、召されて使徒となったパウロから、―― (1章1節)
《僕》とは「奴隷」のことです。わたしたちの国に奴隷制度はありませんが、奴隷のように自由を奪われ、人権を踏みにじられて生きている人はけっして少なくありません。何かの雑誌で「社畜」という言葉を目にしました。「会社+家畜」から来た造語で、会社に飼い慣らされ、転勤やサービス残業も厭わず、会社に都合のいいように働く賃金労働者を揶揄する言葉、あるいはそういう自分を自嘲する言葉だそうです。身の毛もよだつ言葉です。
しかし、どうでしょうか。わたしたちはほんとうに自由な人間として生きているでしょうか。自由とは何でしょうか。ひとりで、何にも束縛されないで、風の向くまま気の向くままに生きることでしょうか。
そういう自由にあこがれる人もいるでしょう。しかし、現実的に考えてみてください。そういう自由を味わうためには、心配しないでもいいぐらいの健康やお金が必要でしょう。そうすると、結局、健康やお金に心を捕らわれた生活をするようになるのではないでしょうか。健康やお金からも自由にならなければ、ほんとうの自由がある、とは言えないのです。
他方で、両親に愛され、保護されている子どもたちを考えてください。両親のもとにいることによって、子どもは自由に、屈託なく、生きることができます。健康のことも、お金のことも心配しません。多くのひとがそのような子ども時代を過ごした記憶があるのではないでしょうか。
それなのに、やがてその両親の愛が束縛に思えて来て、そこを飛び出してしまいます。それで自由になったのかと言えば、けっしてそんことはありません。今まで心配しなくてもよかった健康や、お金のことや、すべてを自分で心配しなくてはならなくなります。そのために、したくない仕事をしたり、下げたくない頭を下げたり、あれこれ周囲への気遣いで心をすり減らしてしまうのです。畢竟、自分は社畜だと自嘲したり、「生きづらさ」「居場所のなさ」を感じる人も出てくるのです。
パウロは違います。自分は《キリスト・イエスの僕》であると胸を張っていうのです。《僕》とは奴隷のことであると申しました。それならば、《キリスト・イエスの僕》とは、自分の命も、権利も、すべてをイエスさまの御手に預けてしまった者ということになります。
そんなことができるのは、パウロがイエスさまがだれであるかをよく知っているからです。イエスさまは救い主です。わたしたちを愛してくださる方です。イエスさまの教え、導きは、つねにわたしたちに命を与えものです。そのことに何の疑いもないからこそ、イエスさまにすべてをお委ねすることができるのです。パウロにとって、《キリスト・イエスの僕》とは、なにものも恐れずにキリストの愛のもとに生き、なにものにも縛られずにキリストの戒めの許に生きる者だ、ということに他ならないのです。
ルターは、1517年に「95箇条の提題」を世に問うた後、1520年に『キリスト者の自由』という小さな書物を書きました。イエスさまによってのみ救われるということは、イエスさまに満たされているならば、ほかのすべてのものから自由に生きられる、ということである。それが真の自由である、と書いた書物です。
ルターが作詞・作曲した讃美歌『神はわがやぐら』(1954年版『讃美歌』267番)も、同じことを歌っています。どんな力が自分を襲ってくるとしても(1節)、どんな戦いに挑むなければならないとしても(2節)、サタンの脅かしがあろうとも(3節)、大切な人、自分の命が奪い取られようとも(4節)、イエスさまの愛と戒めに生きる自分を失うことはない、ということです。
このパウロの気持ちは、詩編23編を詠んだダビデの気持ちと同じだったと思います。ダビデは、わたしは誰にも飼われていない自由な羊だとは言いません。わたしは主に飼われてる羊である、主はわたしの羊飼いである、というのです。しかし、だからこそ死の陰の谷をゆくときも、敵を目の前にしても、恐れや不安に支配されることなく、自分らしく自由に生きられるのだ、とダビデは讃美します。パウロは、わたしは《キリスト・イエスの僕》である、というのはそれと同じ心境であったに違いありません。
|
|
|
|
|
|
ところで、自由であれば、人間は幸せなのでしょうか。自由も大事ですが、その自由をもって何をするか、どう生きるか、ということが、それ以上に大事であるように思います。
内村鑑三の弟子である黒崎幸吉は、パウロが《キリスト・イエスの僕》といったとき、その精神は「奴隷」と言うよりも日本の封建時代の「家臣」に近いといっています(注1)。封建時代の家臣といえば武士です。武士は、誇り高き家臣です。「武士道とは死ぬことと見つけたり」という有名な言葉があります。武士は、主君のために、あるいは自分の誇りのためには、死ぬことさえ恐れません。いや、恐れていたのかもしれませんが、そのような死から逃げ出そうとはしませんでした。彼らが最も恐れたのは、犬死することです。死ぬに価しないことのために死んでいくことを恐れ、不名誉としました。主君に忠誠を尽くすことは武士の誠であり、主君のために命を投げ捨てるのは武士の勇気、名誉でした。
わたしたちは死を恐れ、身を守ることばかりを考えるために、ほんとうの生き方も出来なくなってしまうことがあるのではないでしょうか。逆に「このことのためならば、死んでもいい」という生き方を見いだすとき、わたしたちは大きな喜びをい見いだし、自分の生き方を貫く力を得ることができるのです。
ヨーロッパには、古くから、「メメント・モリ」という言葉があります。「死を思え」という意味のラテン語です。死を忌むべきものとして考えないで生きるのではなく、人間は死ぬものであるということを覚えるとき、かえって「自分は何のために生き、また死んでいくのか」、「自分のいのちをかけてもいいものは何か」ということを、真剣に求め、考えるようになるのです。
そこからインスピレーションを与えられてのことだと思いますが、カトリックのシスターであり、教育者としても著名な渡辺和子さん(1927-2016)は、ときどき「リトル・デス」という言葉をつぶやくのだ、と書物のなかで語っておられます。どの書物であったか忘れましたが、「リトル・デス」という言葉を印象深く覚えています。
日々の生活のなかで、わたしたちは、自分の思いのままに生きるのではなく、自分を律して生きなければならないことが多くあります。そうしなければ、ほかならぬ自分自身が愚か者になってしまうことがあるのです。イライラしたとき、欲をかいたとき、恐れたとき、怠惰な気持ちになるとき・・・そのような時、小さな声で「リトル・デス」(小さな死)とつぶやいてみる。自分を守るのではなく捨てること、自分を生かすのではなく殺すこと、それによってこそ自分のいのちを尊いものされていることを思い出してみるのです。そこに死でさえからも自由とされた、キリスト・イエスの僕としての生き方があるからです。
(注1) 黒崎幸吉、『注解 新約聖書 ロマ書・ガラテヤ書』、日英堂、1939年、3頁
|
|
|
|
|
|
パウロは、自分がそのような誇りある、そして喜びある《キリスト・イエスの僕》となることができたのは、イエスさまによって《選び出され、召され》たからである、と言っています。自分が「わたしはイエスさまを信じる」、「イエスさまのしもべになる」と言っているだけでは、イエスさまのしもべになれないのです。イエスさまが、わたしたちを御自分の僕として認めてくださらなければ、わたしたちはイエスさまの僕にはなれません。ですから、イエスさまによって《選び出され、召され》ということが極めて大事な意味をもってきます。
戦国末期、宮本武蔵という剣豪がいました。当時、腕に覚えのある者たちは、他流試合など盛んにして、有力な武将や大名に認められ、家臣になるためであったと言われています。宮本武蔵もそうでした。彼は、13歳から29歳までの間に、60の試合をし、すべてに勝利を収めたといいます。しかし、仕官の望みは叶えられませんでした。理由はいろいろあるようですが、いずれにせよ、武蔵を家臣として召してくれる主君がいなかったのです。ようやくの落ち着いたところは、肥後藩の客分という身分でした。
わたしたちも同じです。わたしたちの思い、わたしたちの行いで、イエスさまの弟子になれるのではありません。たとえ願っても、召してくださる方がいなければ、仕えることがでません。
しかし、イエスさまは、罪深いままのわたしたちを憐れんで、「わたしに従いなさい」と仰って下さいました。イエスさまとわたしたちの関係は、このようにイエスさまご自身が築いて下さるものであるということを忘れてはいけません。それを恵みとして受け止めた者だけが、《キリスト・イエスの僕》として生きることができるのです。
パウロは自分を誇って《キリスト・イエスの僕》と言っているのではありません。自分を召し出してくださったイエスさまの恵みを喜び、感謝しているのです。わたしたちが、クリスチャンであるということもまったく同じです。わたしたちを愛し、わたしたちにまことの命を与えようとして、イエスさまが招いてくださったからこそ、わたしたちはクリスチャンとなることができました。その喜び、感謝をもって、自分がクリスチャンであると言える者でありたいと願います。
|
|
 |
| 目次 |
|

|
|
| 聖書 新共同訳: |
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible
Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|