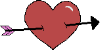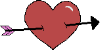|
|
|
|
|
『創世記』の説教を始めて、一年になりました。一年が経っても、まだ3章が終わっていません。それだけ丁寧に読み進んできたともいえますが、正直を言えば、それだけつかえつかえ読んできた気がします。
みなさんもきっとそうだと思いますが、わたしも聖書を読んでいますと、いろいろな疑問が湧いてきます。疑問には、勉強して分かる解釈上の疑問と、そうでないものがあります。勉強では解決できない疑問は、単に解釈上の問題ではなく、人生の根本問題に関係があるのです。わたしは、そういう疑問をできるだけ大事にして、みなさんにお話ししてきました。そういう疑問こそ、生きていく上でどうしても考えなければならない大切な疑問だからです。その答えいかんによって、私たちの信仰や生き方が左右されるのです。
そういう疑問を、簡単に通り過ぎてしまわないで、立ち止まって、いったい聖書はこの疑問に対して何を語ろうとしているのかを、一生懸命に考えてみることが大事だと思います。答えが出れば、それこそ信仰や人生において大切な気づきになります。答えが出なくても、鶏が卵を抱くように疑問を抱えておりますと、いつかハッと気づかされることがあるのです。
わたし自身、この一年間、『創世記』を読んできて気づかされたこと、また卵のように抱えている疑問がたくさんあります。その中で、特に大きな気づきであった二つのことをお話ししたいと思います。
|
|
|
|
|
|
ひとつは、この世界の本質は闇であるということです。この夏休み、子どもたちとしばらく星空を眺める時間がありました。ペルセウス座流星群が見られる日です。夜中の0時頃、空を見ると曇り空で星はまったく見えませんでした。しかし、朝4時頃に目覚めて空を見ると、よく晴れていて満天の星空でした。そこで、子どもたちを起こして、一緒に星を見たのです。
いくつもの流れ星を見ることができました。わたしは、夜空を見ながら、神様の天地創造の話しを思い起こしていました。空には、ほんとうにたくさんの星があります。無数の星がごちゃごちゃと固まって見えるものもあります。しかし、この賑やかさは見かけ上のことで、実際に宇宙に出てみたら、星と星の間には果てしない闇が、そして沈黙が広がっているのです。
そういう宇宙の片隅に、わたしたちが住んでいる地球がポツンと存在しています。神様は、この地球を、水と緑と命の溢れる星としてお造りになりました。この果てしない宇宙のどこかに、神様は他にも地球と同じような星を造られているかもしれません。人間と同じような命をお造りになっているかもしれません。しかし、たとえそうだとしても、それは隣人とはなりえないほど遠くにいることだけは確かなようです。
そんなことを考えていましたら、ふとした疑問が起こってきました。いったい、神様はなぜこんなに大きな宇宙をお造りになったのだろうか? もし天地創造の目的が、わたしがお話ししてきましたように人間の創造ということにあるならば、こんなに果てしない底なし沼のような宇宙の広がりが必要だったのだろうか? そういう疑問です。
そしたら、ふと『創世記』1章2節のみ言葉を思い起こしたのです。
地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。
わたしは、この部分について説教をした時、「光よりも闇が先にあった。この世界の本質は闇である」というお話しをしました。星空を見ていると、「ああ、本当に深い深い闇の中に、その深淵にわたしたちの地球はあり、その中でさらに小さな砂粒のような自分が今ここで生きているんだなあという実感がこみ上げてきたのでした。
なぜ、神様がこんなに広い、深い、宇宙という闇をお造りになったのか、この大きすぎる闇にどんな必要性があるのか、それは分かりません。しかし、少なくとも、わたしたちは自分の力では決して抜け出せない闇の中にいるのです。それは、わたしたちを神様の前に謙遜なものにするに十分な闇です。
人間は科学にしろ、哲学にしろ、宗教にしろ、いろいろなことを考え、いろいろなことを造りだしてきましたが、そんなものは宇宙の外から見たら、いったいどんな光を放っているというのでしょうか? わたしたちを取り囲む深い闇の中に埋もれてしまうものばかりなのではないでしょうか。おそらく一瞬の煌めきである流れ星ほどもないに違いありません。
しかし、聖書は、そのような闇のなかに、神様が言葉を投げかけられたと語っています。その神様の言葉が光となって輝き、この世界を形作り、命を生み出したと語るのです。そして、それを良しとされたと語るのです。無神論者は、それさえも人間の作り話だと言うでしょう。しかし、わたしたちの生活の実感からしますと、無神論者の話の方がよほど作り話に思えるのも事実なのです。
また夏休みの話しですが、ほとんど20年ぶりに高校時代の友人に会いました。わたしは、あまりいい高校時代を過ごしていたとはいえませんので、あまり多くの友人はいません。それでも、高校を卒業してから結婚する頃まで、しばらくは夏休みになると一緒に遊んだりしていた二人の友人がいました。それも結婚後はほとんど会わなくなって、そまま音信もなかったのです。
ところが、去年の夏休み、その一人と奇跡的な邂逅を果たしました。家族で動物園にいきまして、ベンチに坐ってお昼を食べていますと、その真向かい2メートルぐらい先に、わたしと向き合って彼がやはり家族と一緒に坐ってお昼を食べていたのです。最初は、似ているなあと思いながら、お昼を食べていました。そして、わたしの方がその場を離れようとしたときに、彼の方から「失礼ですが・・」と声をかけてくれ、そこでお互いを確かめ合ったのでした。
その彼と、今年の夏、あらためて会ったのですが、彼は「俺は神様を信じてないけど、偶然というにはできすぎている、神様が引き合わせてくれたに違いない」と言っていました。このように、神様を信じたくなるような出来事というのは、信じる者だけに起こるのではありません。わたしたちの生活の中には、「偶然」ではなく「奇蹟」として考えた方が納得できることが、多くあるのではありませんでしょうか。
それはともかくとしまして、わたしはこの闇の中に閉ざされた自分の人生、この世界に、光として輝くものを信じることができる幸いを、改めて感謝をしたのでした。それは闇というものを意識すればするほど、大きな感謝なのです。
|
|
|
|
|
|
もう一つのことは、なぜ、神様は善悪の知識の木の実を食べてはいけないと、命じられたのかということです。普通に考えれば、善悪の知識を持つことは、よいことなのです。それを知らないことこそ、非難されるべきことであり、善悪を知ることが非難されるという話しは聞いたことがありません。けれども、聖書は、善悪の知識を身につけたことこそ、人間の原罪であり、諸悪の根源であると語るのです。
わたしは、この疑問を子どもの頃から抱いてきました。しかし、これまでついに突き詰めて考えることをしてこなかったのです。それが善悪の知識の木だろうと何の木だろうと、神様が食べるなと言ったのに食べてしまった、それが罪だと思い込もうとしてきたと思います。実際、教会では、そのように教えられてきたのも事実です。禁断の木の実を食べてしまったことが原罪である、と。
しかし、「禁断の木の実」という言い方には誤魔化しがあります。それが「善悪の知識の木の実」であることを、どこかでうやむやにしているのです。神様が問題にされていることは、食べてはいけないと言った木から取って食べたというだけではなく、3章22節にありますように、人間が神のように善悪を知る者となってしまったことにあるのです。
なぜ、人間が善悪の知識を持つことがいけないのか、わたしはこの話しを読むたびに、小骨が喉に刺さったように、いつもチクチクと感じていました。それを今回、『創世記』の説教をするにあたって、避けては通れないこととして、聖書に向き合いました。そして、たしかに聖書のいうとおり、善悪の知識を持ったことこそ人間の不幸の源であることを、はっきりを理解できたのです。
第一に、善悪の知識は、わたしたちに罪の意識をもたらします。善悪を知れば、人間は良いことだけを選び、悪いことをしなくなるのではありません。こういう短歌があります。
これつきり、これつきりつて手を伸ばし堕落楽しむポテトチップス(古志 香)
こんなに食べていると太ってしまう、太るということは、女性として堕落することだと分かっている。しかし「ダメ、ダメ、これが最後」と思いながら、ポテトチップスから手を引けない。人間の本質を見事についたとっても旨い歌です。簡単にいえば、「わかっちゃいるけどやめられない」ということでしょう。
人間は善悪を知ったところで、善だけを選ぶ人間になるわけではありません。そのために、この歌にも「堕落」という罪意識を滲ませた言葉がありますが、善悪の知識がわたしたちにもたらすのは、罪意識だけなのです。それは、聖書も言っていることです。律法(善悪の知識)は、わたしたちを善い人間にすることではなく、罪を自覚した人間にするためのものだ、と。
わたしは意志の弱い人間ですから、若いときからこの罪意識に苦しんできました。子どもの頃から教会に通っていたぶん、他のひとよりも厳しい善悪の知識をもっていたこととも関係があるかもしれません。しかし、一番の問題は、善悪を知ることによって、自分は善い人間になれると信じてきたにあったのです。本当は、そんなことできないのが人間なのに、できると思い込んでしまう。ですから、自分は悪を慕うばかりのどうしようもない悪い人間だ。わたしのような人間は、神様を悲しませるだけで、生きている価値もないのだと、そう思ってきました。わたしの善悪の知識というのは、そのように自分を裁き、自己否定し、自分に罰を与えようとすることばかりを与えてきたのです。
第二に、善悪の知識は、わたしたちを偽善者にします。それは、今申しましたような罪意識から逃れようとする結果です。わずかな善を誇ることによって、多くの悪を隠す。あるいは見かけ上の善を行って、心の醜さを隠す。そうやって、本当の自分の姿を、自分の目からも、他人も目からも隠そうとすること、それが偽善です。
偽善の一番の問題は、それによって神様をも欺き、天国に入れる資格を得ることができると思い込み、神様を侮ってしまうことにありましょう。イエス様の山上の説教を読みますと、そういう偽善によって、神様を侮っている人たちへの警告の言葉がたくさんあります。そんな上っ面の偽善を誇り、神様を欺けると思ってはいけないということです。裏を返せば、そんなことをするよりも、自分の罪深さを悲しんでいる人間の方が、ずっと神様に対して真摯な存在なのだというのです。
第三に、善悪の知識は、他人を裁きます。そして、ゆるせず、受容できなくなってしまいます。善悪の知識が、善と悪を相容れないものとする思想をもたらしまして、ゆるすということを非常に困難なものにするのです。また短歌の話しで恐縮なのですが、短歌雑誌の今月号にこういう歌が掲載されていました。
煙突の片側のみが濡れてをり中途半端といふはやさしき(谷川翡翠)
他の歌も何首かあるのですが、それをみますと作者は長年会社勤めをしてきたサラリーマンのようです。サラリーマンにとっての善悪は、会社に利益をもたらすかどうかということにあるのでありましょう。またそれに関連しますが、合理性が大事にされるのが、サラリーマンの世界です。不合理なことや、不利益をもたらす者は、容赦なく裁かれる。そういう厳しい世界に身をおいてきて、作者は「中途半端といふはやさしき」という味わい深い言葉を語ります。善とも悪ともつかないもの、善をごり押ししないで悪を容認するあり方、その中途半端さこそ、実は人間がホッとする場であるということなのです。しかし、善悪の知識を信仰する人間には、なかなかこの優しさがもてないのです。
第四に、善悪の知識は、人間を不信仰にします。自分の善悪の知識で神様の御業をはかり、「神様はなぜこんなことをなさるのか」、「なぜこんなことをゆるしておられるのか」と、自分を裁くだけではなく、あるいは他人を裁くだけではなく、神様さえも裁く人間になってしまうのです。
たとえば、イエス様が、「わたしは近いうちにエルサレムで迫害され、殉教するだろう」と、弟子たちに予告されました。すると、ペトロは、「主よ、そんなことを仰ってはいけません」と、イエス様を諫めたとあります。ペトロにしてみれば、正しい方であるイエス様がそんな目にあうことがゆるせなかったのでありましょうが、イエス様は、「サタンよ、引き下がれ。あなたは神のことではなく、人間のことを思っている」と、ペトロを厳しく叱られました。人間の持つ善悪の知識は、実はそれこそ不徹底なもの、中途半端なものに違いありません。それを神様以上に絶対化してしまうことが問題なのです。
このように考えてみますと、人間を不幸にしているのは、確かに善悪の知識ではないかと思えてきます。神様は、善悪の知識の木を食べてはいけないと言われました。つまり、神様ははじめ人間を善悪の知識を持たない者としてお造りになったのです。では、善悪の知識をもたない人間は、何を判断基準にするように造られたのでしょうか。それは、神様のみ言葉です。この混沌とした闇の深い世界に、光となって輝き、秩序ある形を与え、命を生み出し、それを支えておられるみ言葉です。ただこのみ言葉のみをわたしたちの支えとし、道として生きること、それが神様の愛を受け入れる信仰であり、人間の幸せだったのでした。
わたしは、このように気づきつつも、今もやはり善悪に拘る自分がいることを感じています。そして、自分を責めたり、他人を責めたり、神様を責めたりしているのです。しかし、そんな人間であるわたしの全部を、神様は愛をもって包んでくださっている。イエス様の十字架が、そのことをわたしに語りかけてくれます。イエス様の十字架は、ペトロが言ったように、善悪ではかれば決してあってはならないことです。しかし、神様は、愛をもってそれをしてくださいました。その神様のお心を知るとき、わたしは本当に救われた思いがするのです。これでいいのだ。神様は、わたしの罪も、愚かさも、ぜんぶを許して、わたしの愛の中に生きよと言ってくださっているのだと、感じるのです。
神様が、わたしたちに願っているのは、立派な人間、間違いのない人間、賢い人間であることではないのです。神様がわたしたちに願っているのは、わたしたちが幸せになることです。神様に与えられた生を喜び、感謝し、讃美して生きる者になることです。罪深くあっても、愚かであっても、神様の愛を信じ、そのみ言葉にいきるとき、わたしたちはそのように生きることができるのです。
|
|
|
|
|
|
そう思えたとき、わたしはまた一つ、新しい気づきを与えられました。3章19節、
塵にすぎないお前は塵に帰る
《塵》とは、価値のないものの譬えでありましょう。神様はわたし達を塵から取られ、形作り、命を吹き込んで、神様が愛してくださるような存在としてくださいました。しかし、やがて《塵に帰る》とは、また元の木阿弥になってしまう。人間は罪を犯したために死に、所詮、塵に過ぎないものに帰結していくのだ。それが罪を犯した人間に課せられた神様の呪いなのだと、今までそんな風にここを読んできました。
しかし、それだけでありましょうか。もともと塵であったわたしたちが、自分が神のであるかのように生きてしまっている。そのために、自分を裁いたり、他人を裁いたり、神様をさえ裁いたりしている。そして、傷つけ合って生きている。そんなわたしたちが、もう一度、塵に帰るということに、わたしは慰めを、安らぎを感じるのです。
決して厭世的な意味ではありません。塵に帰るというのは、滅びではなく、もとの姿に戻れるということなのです。もう一度、塵になって、神様の御手のなかに自分を委ねる者になることができるのです。別の言い方をしますと、わたしたちはすでに死んでいるのです。神様がわたしたちにお与えくださった命を失っているのです。それがもう一度、塵に戻れるということは、むしろ、新しい命への希望があることではないかということです。だからこそ、死は、今のどうしようもない人生に対する慰めであり、安らぎ、もっと言えば希望なのではないかと思うのです。 |
|
 |
| 目次 |
|

|
|
|
|
聖書 新共同訳:
|
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|