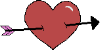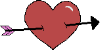|
|
|
|
私たちの国では古来より「八百万の神」と言いまして、神様はたくさんいるという考えがあります。それどころか、死んだ人が神になるという考えまであって、どんどん神様の数が増えていくと言ってもいいでしょう。神様の数が一番増えたのは江戸時代で、その頃になりますと庶民たちの文化というものが花開きます。人間の生活が文化的になると、悩みも文化的になるといいますか、学問をしたいとか、金持ちになりたいとか、これこれの仕事に就きたいとか、お洒落をしたいとか、身分を超えて自由な恋愛をしたいとか、いろいろ複雑で、贅沢な悩みが増えてきます。そういう肥大化した人間の悩みや願いに比例して、金持ちになる神様、学問の神様、恋愛の神様と、神様の数もだんだん増えていったのです。
獄門にされた大泥棒が縁結びの神様になったという話を聞いたことがあります。この大泥棒は死んでからも人々に憎まれ、その墓をみんなから踏みつけられた。ところが「踏みつけ」がいつの間にか「文つけ」と駄洒落的に解釈されるようになり、縁結びの神様となったというのです。また、江戸時代には「願掛重宝記」なる神様のガイドブックもあったそうです。これこれの願い事には、どこそこの神様がよく効くとか、願掛けの作法、お礼参りの作法などが詳しく書いてあるそうです。こういうことがよく表していると思うのですが、八百万の神というのは、人間のお願い事が中心でありまして、人間の願望がいろいろな神様を作り出しているんですね。
これは現代も同じです。江戸時代というのは厳しい身分差別があったり、貧富の差があったり、今に比べたら自由もないし、食べていくこと、生きていくことがたいへんな時代でありました。そういう意味で、江戸時代の神頼みには生きるための切実さがありました。それに対して今は、神頼みをしなくても、たいていのことは人間の力でかなってしまう時代です。誰もが生まれながらにして平等で、基本的人権が保障され、身を粉にして働かなくても何となく食べていけるし、お国のために命を捨てろとも言われないし、平均寿命は世界一となっている。それは、一昔前から言えば「幸せ」なことなんですね。ところがそういう幸せを享受していても、神頼みはなくなりません。江戸時代の御利益宗教とはちょっと違いますが、オカルトとか、占いとか、スリピチャルとか、ニューエイジとか、得体の知れない新宗教が大流行をしているわけです。
その根底にあるのは、不安です。物質的にも満たされ、教育も受け、人権も守られ、申し分ない環境の中に生きていましても、人間の心の根底にはぬぐい去れない不安があるのです。その不安の正体こそが人間の罪であると申し上げたいのですが、それは後ほどまたお話しさせていただきます。いずれせよ、現代の宗教というのも、生きるための切実な願いが、生きていることへの得体の知れない不安に取って変わっただけで、結局は人間の心が、神様を呼び求め、神様を造っているということには変わりがないのです。
それに対して聖書の神様は、唯一の神様です。人間の願いの数だけ神様が生まれてくるような日本の多神教とは違いまして、生きるためのすべての必要、人間の根底に横たわるすべての不安、そういうものを一手に引き受け給う神様なのです。それからもうひとつ、神様は人間に呼びかけ給う神であると言われています。今も申しましたように御利益宗教の神々というのは、人間の願望が生み出した神々です。そこで中心になるのは人間の願い、祈りです。しかし、聖書が教えていることは、神様が人間を呼び求めており、その声に聞き従うことこそが幸せの道であるということなのです。それは神様が唯一の方であって、人間のすべてを満たし給うことができるお方であるということと深い関わりがあります。神様が二人も三人もいたら、私たちはいったいどの神様に聞き従えばいいのか分からなくなってしまう。ですから、多神教では、神様に聞き従うということは出てきません。出てきたとしても、非常に限定的なことなのです。
しかし、聖書の神様は、私たちの全存在をかけて聞き従うことを求めておられる神様であるということなのです。『ヘブライ人への手紙』1章1-2a節にこう書いてありました。
神は、かつて預言者たちによって、多くのかたちで、また多くのしかたで先祖に語られたが、この終わりの時代には、御子によってわたしたちに語られました。
神様が人間に語りかけるということは、神様が人間に関わりを求めているということです。人間が神様を呼び求めるよりも先に、神様が人間を呼び求めている。それに対する応答が信仰です。人間の願いが神様を造り出すのではなく、神様の呼びかけが人間の信仰を呼び覚ます。これが聖書の教えている神様なのです。 |
|
|
|
|
|
なぜ神様が人間を呼び求めるのか、その理由が書いてあるのが『創世記』1〜3章です。神様は、この天と地と海とそこに満ちるすべての生きとし生けるものをお造りになり、それらのものを御自分の祝福のうちに置かれました。特に、人間は「神の形」に似せて特別なものとして造られたと、聖書は記しています。「神の形」というのは、姿形のことではありません。神様はいかなる姿形を持たないお方だからです。では神の形とは何か? それは神のもっておられる愛、正義、善、自由、知恵・・・そういった神様のご性質といいますか、神様のもっておられる神格のことなのです。神様は人間の人格の中に、そのような神様のご性質に似たものをお与えになったのでした。そうすることによって、神様は人間を神の子供らとしてお造りになったのです。ですから、人間の持つ「神の形」とは、人格性のことだと言ってもいいと思います。
人間の人格性の中で特に重要な特徴は自由です。人間以外のものは、すべて神様がお決めになった自然の法則、秩序の中に存在しています。人間だけが、そのような自然の法則を超えて、自分の意志で進むべき道を選び取ることができるのです。それが人間らしさだと言ってもいいでありましょう。マーティン・ルーサー・キング牧師は、自らの黒人解放運動の闘いを自伝に書き留め「自由への大いなる歩み」(岩波新書)と題しました。自由を奪われた人間は非人間的であり、その自由を回復とすることは人間性を取り戻そうとすることであります。まさに大いなる歩みというにふさわしいことでありましょう。
しかし、自由が人間を非人間化することがあります。無責任な自由は単なる我が儘となり、隣人を傷つけ、社会的な連帯を破壊してしまうのです。自由というのは両刃の剣なのです。何でもできることが自由なのではなく、自分にとって本当に大切なものを知り、それを勇気と決断をもって選び取っていくことができることが、人間を人間らしくする自由なのです。
マーティン・ルーサー・キング牧師は、「自由への大いなる歩み」の中で、抑圧された黒人が自由のために闘う苦しさを逃れるために、今ある生活に甘んじる自由もあるが、そのような消極的な自由は単なる諦めであって、決して人間らしいことではないと言っています。また憎しみをもって、暴力をもってこの闘いを戦うこともできるが、それもまた人間らしいことではないと言っています。だから、自由への道を決してあきらめず、しかも非暴力をもって、憎しみではなく白人と黒人との調和を求めて戦い続けることが、抑圧された黒人が人間らしく生きるための唯一の道なのだというのです。このように、自由に生きるとは、このようにあれも自由、これも自由と主張することではなく、本当に人間らしく生きる道は何かということを悟り、それをば求め続けていくことでなければならないのです。
しかし、『創世記』3章で、人間は自由をもって、神様の御心に背き、神様の愛と祝福を捨ててしまったということが書かれています。人間は神様の愛と祝福の中に生き続ける自由を捨てて、神様からの自由を選び取ってしまったのです。分かり易く言えば、神様を捨ててしまったわけです。聖書には、そのために人間はエデンの園を追放されたと書かれているのですが、追放されたというよりも自らそのような道を選び取ってしまったというのが正解でありましょう。エデンいうのは「喜び」という意味です。人間は、我が儘な自由を選び取ることによって、まことの喜びを捨て去り、失ってしまったのです。
聖書はこのような人間を罪人と言っています。罪人というのは人殺し、泥棒、強姦、詐欺というような人間としてあるまじきことを行った人に対して使われますが、それ以上に人間としてあるまじき行いは、造り主なる神様を捨てて、神様との祝福された関係を破壊してしまったことであるというのが、聖書の教えていることなのです。
|
|
|
|
|
|
今日は『ホセア書』7章を併せてお読みしました。ここには神様の愛と祝福を捨て去った罪人の愚かさ、それに対する神様の嘆きが書かれています。9節を読んでみましょう。
他国の人々が彼の力を食い尽くしても
彼はそれに気づかない。
白髪が多くなっても
彼はそれに気づかない。
罪人の愚かさ、それは自分たちの不幸に気づかないということです。そして、気づいたとしても、まだ自分は大丈夫だと高をくくっているのです。10-11節、
イスラエルを罪に落とすのは自らの高慢である。
彼らは神なる主に帰らず
これらすべてのことがあっても
主を尋ね求めようとしない。
エフライムは鳩のようだ。
愚かで、悟りがない。
エジプトに助けを求め
あるいは、アッシリアに頼って行く。
《これらすべてのことがあっても》というのは、どんなに失敗し、痛い目にあっても、ということです。それでも、神様に救いを求めないで、自分の力で何とかなると思っている。エジプトとか、アッシリアとか、そういうこの世の力を頼みとし続け、あくまでも神様には背を向けたまま、決して神様に立ち帰ろうとはしない。それが高慢で、愚かで、悟りがない罪人の姿であると言われています。続いて13-14節、
なんと災いなことか。彼らはわたしから離れ去った。
わたしに背いたから、彼らは滅びる。
どんなに彼らを救おうとしても
彼らはわたしに偽って語る。
彼らは心からわたしの助けを求めようとはしない。
寝床の上で泣き叫び
穀物と新しい酒を求めて身を傷つけるが
わたしには背を向けている。
神様が救おうとしてくださっているのに、神様に救いを求めないと言われています。寝床で泣き叫び、暴飲暴食つまり自棄(やけ)をおこしたり、自分を傷つけたりすることがあっても、「神様、助けてください」と心から救いを求めようとしないというのです。こういう罪人を端的に一言で言い表した言葉があります。それは16節に出てくる《ねじれた弓》です。
彼らは戻ってきたが
ねじれた弓のようにむなしいものに向かった。
《ねじれた弓》は、どんなに的に向かって照準を合わせても、矢は的を逸れて流れていきます。それと同じように、神様を離れた罪人のやることは、何をやっても的はずれになってしまうというのです。喜びを求めても、悲しみしか生み出さない。自由を求めても、より不自由になるばかり。愛を求めても、果ては傷つけ合ってしまう。どうしてか。神様の愛を祝福を失った人間は《ねじれた弓》だからです。目標は正しくても、そのためにどんなに努力しても、矢は的を外れてしまうのです。それが罪人の姿なのです。 |
|
|
|
|
|
森有正(1911-1976)の『いかに生きるか』(講談社現代新書)という本を読みました。フランス文学、哲学の専門で、敬虔なプロテスタント信仰をお持ちだった方です。ある時、森有正が宮城学院女子大学の夏期講座を終えて教室を出ますと、一人の学生がやってきて「先生はなぜ生きておられるのですか」と質問してきたそうです。森有正は「私はなぜ生きているかというと、私はもうじき死ぬから生きているのです。私は死ぬために生きているのです」と答えられたと書いてあります。
死ぬために生きるとはどういうことか。森有正という人は、人生というのは経験の積み重ねだから、その経験について考えを深め、その中に自分を見いだして成熟させていくことによって、しっかりとした人格を形成できるし、生きる道も明らかになるということを言っています。そして、そういう経験の最後にくるのは「死」なのです。経験、経験と言って生きてきても、最後の経験である死をもってそれが終わるわけです。ですから、森有正は自分の人生を完成させるような死を死にたい。納得のいく死を遂げたいということを真剣に考えるんですね。
ところが、そういうことを考えていくうちに、森有正は一つの行き詰まりに気づくのです。それは罪の問題です。
私たちが、私たち人間の経験の問題を深く考えてみると、その経験の問題そのもののいちばん根底にあるのは、けっきょく罪の問題だということです。罪とはどういうことか、それは経験の立場から申しますと、自分の経験が自分というものを生み出す、あるいは、自分というものを自覚させる、そこに私たちの人生のすべての意味が込められているわけです。・・・しかし一つの経験は、それが充足しようとするときに、ほとんど常に他の経験を傷つける、あるいは他の経験から傷つけられる、ときには他の経験を滅ぼすということもおこってきます。・・・キリストが言われたように、現に行いに現れただけでなく、私たちの心の底においても、他の人の経験が傷つけられ、弱められ、破られることを願っている場合があります。そういうことを願っているならば、私の経験が他の人から尊重されることを望む権利は何もないわけです。(『いかに生きるか』、178-179頁)
つまり、自分の経験を大事にして深めていくことはいいけれども、そこで他者の経験を傷つけている。それは避けられないこととして起こっている。そういうことを無視して、自分の経験ばかりを深めて、私の人生にはこういう意味があったなんて誇ったところで、まったく空しい。この罪の問題を処理しなくては、とても最後の経験である死を納得いく形で迎えることはできないということなのです。
物質的に満たされていようが、立派な教育を受けていようが、ぬぐい去れない不安があるというのは、このような罪の存在なのです。どんなに一生懸命に生きていても、お前は他者を傷つけ、その犠牲の上でいい思いをしてきただけじゃないかと言われたら、いっぺんに自分の人生の価値というものが崩れ去ってしまう。これも一種の《的はずれ》現象ですね。そういうことを森有正のような人も感じていた。罪というのは、自分の人生のなにもかも駄目してしまうものなのであって、それが解決されない限り安らかに死ねないというわけです。
そして、森有正はこういうことを言うのです。ちょっと長いのですが、とても重要なことを言っていますので我慢してお聞き下さい。
重要なことは、そのキリストが私たちの語られるメッセージのもっとも中心的な問題が、私たちの罪の問題だということなのです。罪の赦し、これは使徒信条に書いてあるから、重大だと思うのでは駄目で、実は、私たちの信仰生活において、また私たちの人間としての経験において、罪がある限り、人間は死んでも死にきれないということを掴むことです。自分の経験を深めていきますと、その問題だけが残ります。いつでもそれだけが最後に一つ、のどに鯛の骨がささったように、すべてのものがうまく行っても、それだけは残るのです。私たちの力を決定的に超越したものとして、その罪の問題だけが残ります。・・・
私はそれだけがキリスト教の、根本的な中心教理だということを、ここで強調したいと思います。これはけっして単に私の主観ではなく、ほんとうにそれを考えることだけが、私たちの真の安らかさを与える、唯一の鍵なのです。・・・
ある人はこういう罪を持っている、ある人はああいう罪を、しかしみんな、あれこれの罪を持っているのです。みんなが、それを苦しんでいます。それがその人の安らかさを奪っています。それなのに、いちばん人間が言いたがらないことなのです。神に対してさえ隠そうとするのです。あのサマリアの女のように、キリストが最後まで行ってその壁を突き破いても、まだ隠そうとするのです。その不安を抱いたまま、みんな死んでいくのです。
けれども、イエスを信じ、イエスの言葉を信じ、ことに罪の赦しの福音を信じるとき、これはもう信ずる以外にないから、私は説明できませんけれども、そのときに私たちの魂に、本当の安らかさが来ます。信仰というのは、経験ではないけれども、一つの事実です。
とても大事なことを言っておられます。一つは、人間が一番の根底に抱えているのは罪であるということです。罪こそが人間の安らかさを奪い、そしてその不安を抱いたまま死ぬ者としているのだというのです。しかし、この罪の問題は、人間の力を超えた力でなければ解決することはできない。そして、キリスト教というのは、この罪のゆるしを語ることにこそ力があるのだと言っているのです。 |
|
|
|
|
|
『ヘブライ人の手紙』は、神様の愛と祝福を捨ててしまった、高慢で、愚かで、悟りがない罪人である人間に対して、神様がなお呼び求めておられるのだというメッセージをもって始まります。「神、語り給へり」、「神、御子によりて我らに語り給へり」それはなぜなのか。それはひとえに、神様が愛なる神様であるからに他ならないのです。こんな箸にも棒にかからない罪人を、神様はなお愛し、御自分のもとへ回復させようとしてくださっている。それが聖書の福音だというのです。
先ほど紹介したホセアという預言者は、たいへん可愛そうな預言者でありました。彼はゴメルという女性と結婚するのですが、彼女はとんでもない尻軽女でありまして、すぐに他の男のもとに走ってしまう。ホセアは、そんなゴメルを何度も何度も連れ戻し、お前を本当に幸せにできるのは私なのだよと語りかけ、愛するのです。実際、ゴメルは愛人のもとに走っても、決して幸せを見いだせないんですね。そして、「やっぱりあなたがいいわ」と、ホセアのもとに戻ってくるのです。ところが、また別の愛人をつくってそっちに行ってしまう。ホセアはそういうゴメルを苦しみながらも愛し続け、そういう経験を通して神様の愛の苦しみと深さを語るのです。
『ヘブライ人への手紙』は、御自分を捨てて、御自分に背を向け続けている罪人らに、神様はなおも呼びかけておられる、しかも、ついには御子を私たちにお遣わしになって、「わたしのもとに帰れ」と呼びかけてくださっているのだと語っているのです。御子とは、イエス様のことであります。なぜ、イエス様を御子と呼ぶのでしょうか。それはイエス様と神様が一つであるということを言いたいからです。今日お読みしました『ヘブライ人への手紙』1章3節にはこう書いてありました。
御子は、神の栄光の反映であり、神の本質の完全な現れであって、万物を御自分の力ある言葉によって支えておられます
《神の栄光の反映》というのは、神様の素晴らしさをそっくりそのまま、鏡に映すように映し出しているということです。《神の本質の完全な現れ》という言葉もほとんど同じ意味であります。本質というのは、物事の根源的な姿をいう言葉でありまして、「神とはいかなるお方であるのか」ということを、イエス様が完全に表して見せてくださっているのだということなのです。
つまり、イエス様というお方は、神様と一つなのだ。そういうお方が、私たちと同じ人間となって、私たちの世に宿ってくださった。つまり、イエス様を通して、神様は御自身を私たちに顕してくださったのだということです。本来、目に見えることのない神様が、イエス様のうちに御自分を顕してくださった。だから、イエス様を仰ごうではないか。イエス様を信じて、イエス様に聞こうではないか。『ヘブライ人への手紙』の著者は、そのように私たちに語りかけているのです。
では、イエス様は、どこにおられるのでしょうか? 教会でしょうか? 私たちの心の中でしょうか? それとも私たちを包むように共にいてくださるのでしょうか? 聖書ははっきりとイエス様がおられるところを示しています。それは天の神様の右の座であります。3節、
人々の罪を清められた後、天の高い所におられる大いなる方の右の座にお着きになりました。
《右の座》というのは、右とか左が問題なのではなく、神様に並ぶ方、神様と一つなるお方として、天におられるということです。しかし、ただ天におられるのではありません。《人々の罪を清められた後》とあります。まず、イエス様はこの地上において私たちの罪を清め給う御業を成し遂げられました。イエス様がいかにしてわたしたちの罪を清めてくださったのか、それは十字架ということでありますが、このことについては追々、ヘブライ書を学びながらお話ししていくことになると思います。ただ一つ申し上げれば、それはイエス様にとってもたいへん苦しみに満ちた御業であったということです。それは、十字架の上で《わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか》と祈られたことからも分かるのです。そういう苦しみを、愛をもって引き受けられたイエス様によって、私たちの罪は清められるのであります。
そして、イエス様が天に上られました。そこで神の右の座におつきになりました。それは何を意味するのか? 生ける者と死ねる者とを裁き給う神様の右に、私たちの罪の浄めを遂げ給う救い主がおられるということなのです。これは本当に恵みに満ちたこと、救いに満ちたことです。このイエス様を仰ぎ、このイエス様に聞き従い、このイエス様に私たちの人生を導かれることこそが、人生の平安の道であり、天国に希望をもって安らかにこの世の人生を終えることができる道なのです。御子は罪の浄めを遂げ給う。ここに神様と私たちの関係の回復、そして私たちの本当の安らぎの鍵があるのだということを覚えて感謝をしたいと思います。 |
|
 |
| 目次 |
|

|
|
| 聖書 新共同訳: |
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible
Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|