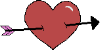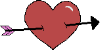|
|
|
|
東京オリンピックにもされた馬術の選手である法華津(ほけつ)寛(ひろし)さんが、44年ぶりに北京オリンピックの選手となって話題となりました。御歳67歳、北京オリンピックに出場した全選手の中で、最も高齢であるということが、外国のメディアからも注目を浴びました。結果はたいへん残念でありまして、法華津さんの愛馬ウィスパー号が、大型スクリーンに驚いてしまい昂奮して暴れてしまったために、本来の力を出せなかったということであります。
この話を聞いて、私はアランの『幸福論』の中にある名馬ブケファラスの話を思い出しました。
名馬ブケファラスが若いアレクサンドロスに贈られた時、どんな名人もこの荒馬を手なずけることができなかった。凡俗な者だったら、あきらめて「まったく性(たち)の悪い馬だ」とでも言っただろう。ところがアレクサンドロスはピンをさがし、たちまち見つけた。ブケファラスは自分の影にひどく怯えているのがわかった。恐怖で飛び上がると影も跳ねるので際限がないのだ。アレクサンドロスは馬の鼻を太陽に向けた。この方向で支えると、馬は落ち着き疲れを示した。こうして、このアリストテレスの教え子はすでに、ほんとうの原因を知らないかぎり、情念を癒すことができないのを知っていた。(アラン、『幸福論』、岩波文庫)
ブケファラスは誰にも手なずけることができない荒馬でありました。それで多くの人はブケファラスを「たちの悪い馬だ」と決めつけたのです。しかし、アレクサンドロスは、この馬をよく観察して、「ピンをさがし、たちまちみつけた」とあります。ピンとは、ブケファラスを荒馬にさせている本当の原因という意味です。その正体は、「自分の影」でありました。大型スクリーンに驚いた法華津さんのウィスパー号と同じですね。それでアレクサンドロスは、ブケファラスの鼻先を太陽に向けさせ、自分の影が見えないようにしたら馬は落ち着きを取り戻したというのです。
アランはこの話から、人間の恐怖について語ります。人間は、恐怖に取り憑かれると、とんでもないことをしでかす。恐怖に取り憑かれるとは、恐れが新たな恐れを育ててしまう。その新たな恐れがさらなる恐れを育ててしまう。恐れがエスカレートしていく状態です。アランは戦争だって、国の指導者たちが恐怖に取り憑かれ、それをエスカレートさせた結果、引きおこされたものであるといいます。いささか極論かもしれませんが、エスカレートしていく恐怖が、理屈に合わない異常な行動、つまり冷静になってみるとどうしてあんなバカなことをしてしまったのだろうと思うような行動に駆り立てるということはよくあることなのです。そして、そのバカな行動をとってしまったために、たいへんな不幸を背負うことになってしまうわけです。
いったいどうすれば恐怖をエスカレートさせずにすむのか? アランはいいます。人間には理屈屋と感情家がいる。理屈屋は、「危険を感じるからこそ恐れるのだ」と言って、その不安(危険)は実際の危険ではなく、本当は感じなくてもいい危険なのだということをおしえてやろうとします。しかし感情家は、そんな理屈屋の言うことに、少しも耳を貸そうとしないのが普通です。「ちがう、恐怖を感じるから危険を感じるのだ」と言うのです。結局、理屈屋は、感情家の恐怖を取り除くことができない。ちょうど人々がブケファラスを「たちの悪い馬だ」と決めつけたように、「あいつは弱虫だからダメだ」とレッテルを貼ってあきらめてしまうのです。アランは、結局、怖がらなくてもいいものを怖がっている感情家も、危険を妄想だと言っている理屈屋も、実はどちらも間違っているといいます。
多くの者が恐怖を、ことばでもってやっつけている。しかも強い論拠をもって。ところが、恐怖を感じている者はその理由など聞かないのだ。彼は心臓の鼓動と血液の波打つ音しか聞かない。
ここが大事なのですが、恐怖の原因は理屈ではなくもっと生理的なもの、心臓とドキドキと血液のドクドクだというわけです。それは理屈屋であろうと、勇猛果敢な軍人であろうと同じだと言うのです。
どんな小さな驚きでさえも人をおびえさせる。まったく危険などないものでも。たとえば、非常に近くで不意にピストルの一発があった時、あるいは思いがけない人が現れただけでも。マッセナ元帥は暗い階段の彫像におびえて、一目散に逃げ出した。
マッセナ元帥とはナポレオンが信頼した勇猛な将軍です。そういう将軍だって、自分の心が作り上げた危険に怯えて逃げ出したことがあった。では、マッセナ元帥は弱虫なのかと言えば、そうではない。耳元で、不意にピストルが鳴れば、誰もが反射的に飛び上がるのと同じことだ、というのです。怖いからドキドキするのではなく、ドキドキする体がわたしたちの脳に「怖がれ!」という命令を出しているのです。だから、恐怖に振り回されないためには、体の反応を上手にコントロールできればいいのだということになります。危険がどうのうこうのという話ではなく、ドキドキとドクドクを少しでも和らげる方法を見つけることが必要なのだということです。
たとえば、雷の怖い人がいる。私はそんなに怖くはないのですが、雷を怖がる人の話を聞くと、その雷鳴を聞き、稲妻をみただけで、からだが硬直してしまうそうです。どうしたらいいのか? そういう人にいくら安全を語ってもダメだし、弱虫と言ってもダメで、ピンをさがし、それを取り除けばいいわけです。この場合、ピンは雷鳴と稲光なのですから、アラン流に考えれば、布団の中に潜るとか、押し入れに閉じこもるとか、ヘッドホンでもして雷鳴が聞こえないようにする。それが一番いいということになるわけです。あるいは子どもであったら、母親や父親がそっと抱きしめてやる。そういうことが恐れを取り除くことになるのです。 |
|
|
|
|
|
なんだか聖書とまったく関係のない話のようですが、私は「ピンをさがす」というアランの言葉が、イエス様の救いということを考える時にもとっても大切なことを示唆しているのではないかと思うのです。アランは言います。
人間というのは意地悪なものだ、と言ってはだめだ。彼がこれこれの性格を持つ、と言ってはだめだ。ピンをさがしたまえ。
たとえば体のどこかに小さなトゲが刺さっている。それが原因でいつもイライラして怒りっぽくなっている人もいましょう。何事も悲観的、消極的になる人もいましょう。あるいはお酒や賭け事や刹那の快楽に逃避して自滅的な生き方をする人もいましょう。そういう人に「あなたの感じ方は間違っている」とか「正しい生き方、考え方はこうだ」と説明するよりも、まずその人のピンを探し当ててあげることが大事だというのです。抱きしめてあげるとか、手を握ってあげるとか、さすってあげるとか、話を聞いてあげるとか、優しい声をかけつづけてあげるとか、ピンをさがして、その痛みや苦しみに寄り添う愛の業、それが大事なのだということなのです。
イエス様の救いもそういうものなのです。少し思慮深い人であれば、人間の罪深さを語ることは簡単です。何が正しい生き方を語ることも簡単です。しかし実際、罪の中にある人間にむかって「あなたは罪人だ。正しい生き方はこうである」といっても、その人は変わることができません。そうすると、「あなたは何をいってもダメだ。根っからの悪人だ。あなたは救われない」と裁いてしまう。イエス様は決してそのようなことをなさいませんでした。イエス様がなさったのは、罪人を裁くことではなく、罪人に愛をもって寄り添い、教えに飢えている者には優しく語り、孤独な者には家に入って共に食事をし、病める者には手触れて癒し、罪人の友となって、それによって神さまの愛を知らしめることだったのです。
一つ聖書をお読みしたいと思います。『マルコによる福音書』14章17-21節
夕方になると、イエスは十二人と一緒にそこへ行かれた。一同が席に着いて食事をしているとき、イエスは言われた。「はっきり言っておくが、あなたがたのうちの一人で、わたしと一緒に食事をしている者が、わたしを裏切ろうとしている。」弟子たちは心を痛めて、「まさかわたしのことでは」と代わる代わる言い始めた。イエスは言われた。「十二人のうちの一人で、わたしと一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。人の子は、聖書に書いてあるとおりに、去って行く。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方が、その者のためによかった。」
最後の晩餐のとき、イエス様が十二弟子に向かって衝撃的な発言をなさいました。「あなたがたの一人がわたしを裏切るだろう」というのです。弟子たちは驚いて「まさか、わたしのことではないでしょうね」と確認します。『マタイによる福音書』26章によりますと、ユダも他の弟子たちと同じように「まさかわたしのことでは」と確認をしたと書かれています。するとイエス様は「それはあなたが自分で言ったことだ」とお答えになります。ユダが幾ら隠そうとしても、その言動がイエス様への裏切りを物語っていたということでありましょう。それを見抜いて、イエス様はここでユダの裏切りを予告されていたのです。名指しで語られているわけではありませんが、イエス様はユダに対して「あなたは不幸だ。あなたは生まれてこなかったほうがよかった。」とまで言っています。
「あなたは不幸だ。あなたは生まれてこなかったほうがよかった。」という言葉は、ユダに対する呪いの言葉に聞こえなくもありません。太宰治の『駆け込み訴え』というユダを題材にした作品がありますが、そこではいったんは裏切りを思いとどまろうとしたユダが、最後の晩餐のおりみんなの前で辱められたためにカッとなって再び裏切りを決意したとなっています。これは文学作品ですから目くじらを立てるようなことではないのですが、実際に聖書に書いてあることを読みますと、そのように解釈するのはちょっと無理があるように思います。
もしイエス様がユダに対して怒りや憎しみや呪いの気持ちを持っておられたのであるならば、ユダを弾劾し、もっと追いつめることだって可能であったと思うのです。イエス様ならばユダに裁きを与え、ユダが裏切らないようにすることもできたはずです。しかし、イエス様はそうはなさらなかった。想像の域を出ない話なのですが、イエス様がユダに「あなたは不幸だ」とおっしゃったのは、ユダに対する深い憐れみではなかったでありましょうか。
「罪を憎んで人を憎まず」と言います。罪が悪いのであって、人が悪いのではないというのは、なんだか無責任な言い逃れのようですが、キリスト教でいう罪というのは、犯罪を犯すことではありません。聖書の「罪」という言葉には「的はずれ」という意味があり、神さまと向き合って生きるはずの人間が、神さまの方を向いていないこと、神さまに背を向けて生きていることをいうのです。どんな人間だって自分なりに一生懸命に生きているのだと思います。しかし、「自分なりに」ということがくせ者でありまして、自分なりに一生懸命に生きているからこそ、自分が的はずれな生き方をしているということになかなか気づかないということがあるのです。気づかなくても、的はずれな生き方は、的はずれな結果を生み出すことになります。ユダも的はずれな道をまっしぐらに進んでいこうとしている。それはユダの中に罪というピンがあるからです。それがユダの理性や悟性や感情を狂わせ、的はずれなものにしているのです。
人間というのは意地悪なものだ、と言ってはだめだ。彼がこれこれの性格を持つ、と言ってはだめだ。ピンをさがしたまえ。
アランはこう言いました。イエス様はそうだったと思います。イエス様はユダを愛しておられた。しかし、そのユダの中には罪というピンがあって、ユダを的はずれな方向にまっしぐらに走らせてしまっている。それはユダ自身を苦しめ、不幸に陥れることが、イエス様には分かっているのです。イエス様は、ユダの存在を受け入れつつ、罪によって的はずれな方向に駆り立てられているユダに「あなたは不幸だ」と言っておられるのです。
イエス様はユダを裁きません。罪を犯すなともいいません。罪のとらわれているユダのそのままの姿を受け入れ、寄り添おうとしておられます。それが実はとっても大事なことなのです。私のようなところにもいろいろな相談が舞い込んできます。「死にたい」とか、「殺したい」とか、「妻子ある人を好きになってしまった」とか・・・私は「ダメだ」とは言いません。とにかく話を聞く。そして、その人の悲しみや悩みに同情し、寄り添ってあげる。すると、時間はかかりますが、「死ななくてよかった」とか、「殺さなくてよかった」とか言ってくれるようになるのです。
罪というピンによって理性や意志や感情を狂わされているのは、ユダに限ったことではありません。わたしたちの誰もが、自分の中に罪というピンを持っている。そして、ユダのようにその罪の存在に気づいていないままに生きているのです。自分は正しいと思っている場合もある。しかし、自分の中に働く罪が、自分を間違った方向へ間違った方向へと導いてしまうわけです。
イエス様は、そのようなわたしたちを裁く御方ではない。むしろ深い同情の心をもって寄り添い、わたしたちをやわらげてくださる御方なのです。だから、『ヘブライ人への手紙』では、イエス様は大祭司と言われるのです。しかも永遠の大祭司、わたしたちを完全に救うことができる大祭司と言われています。祭司というのは、わたしたちの罪を裁く人ではありません。神さまとわたしたちの間に立って、仲を取り持つ働きをしてくださる御方なのです。わたしたちに寄り添いつつ、わたしたちを神さまのもとに導いてくださる、それが大祭司なるイエス様です。7章26節にこう書いてあります。
このように聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ、わたしたちにとって必要な方なのです。
罪というピンに苛まされ、いつも自分の心を狂わされ、間違った感情や欲望に引きずられ、愚かなことを繰り返してばかりいるわたしたちにとって必要なのは、哲学や思想でもなく、処世術でもなく、強い意志でもなく、わたしたちのその悩みを、或る意味でわたしたち以上に知り給う大祭司なるイエス様であるということが言われているわけです。
罪とは、神さまに背を向けて生きていることだと申しました。背を向けて生きているから、神さまが見えません。神さまが見えませんから、ますます自分の罪ということがわかりません。そのようなわたしたちに側に来てくださり、わたしたちに出会い、わたしたちを愛し、受け入れてくださる御方、それがイエス様であります。ですから、わたしたちは、罪深い的はずれな生き方をしながらも、イエス様に出会うことができるわけです。そして、イエス様に出会うことによって神さまを知り、神さまを知ることによって、はじめて自分のこれまでの生き方が的はずれであった、罪深いものであったということにも気づきます。そして罪に気づくことによってはじめて本当の悔い改めもできるようになるのです。
この順序が大切なことです。まず罪を知り、罪を悔い改めて、イエス様を信じ、救われるのではないのです。まだ罪人であったとき、まだ罪というものにまったく気づかないでいるときに、イエス様のほうから寄り添ってくださる。出会ってくださるのです。そのイエス様との出会いがあって、はじめて神さまを知り、それから罪を知るのです。そして、悔い改めが起こり、本当に意味で神さまに向き直って生きるということができるようになるわけです。イエス様こそ、わたしたちが神さまに近づくための希望であり、またそれを実現してくださる救い主なのです。
|
|
|
|
|
|
20-22節には、レビの祭司制度が世襲によるものであるのに対し、イエス様は誓いによる大祭司であると言われています。この誓いというのは、神さま御自身が御自身に誓って、イエス様を大祭司にしたのだということであります。
誓いというのは、自分の言葉を真実なものにするためになされるものでありましょう。とかく自分の言葉が不真実になってしまうわたしたちにとって、誓いによって自分を信じて貰うということは必要なことであります。しかし、真実なる神さまが誓うというのは、本来必要のないことです。その神さまがイエス様を永遠なる大祭司にすると御自身にかけて誓われた。もし、それが損なわれれば、神さまの名折れとなってしまう。それほどまでに、神さまは真実に真実を加えて、イエス様を大祭司になさったのであるということが言われているのです。
また23-24節には、やはりレビの祭司職が死によって多くの人に引き継がれながら続いてきたのに対し、イエス様は復活され、永遠に生きる方であるからその祭司職が誰かほかの人に移ることはないのだと言われています。永遠ということ、これもイエス様の祭司職の確かさを物語っています。
また27-28節は、レビの祭司職にある人は、まず自分自身も罪人であり、その罪の贖いを必要としていたということに対して、イエス様は罪なき御方であったということが言われています。これもまた、イエス様の祭司職の確かさを物語っています。
『ヘブライ人への手紙』が、これだけイエス様の確かさを強調するのは、イエス様の確かさを疑う人がいたからでありましょう。イエス様を疑うといっても、イエス様を否定するわけではありません。しかし、イエス様もたいへん結構だけれども、それだけでは不十分であって、善い行いが必要なんじゃないかとか、割礼とか、モーセの律法や基づく儀式などが必要なのではないかと、当時にはそういうクリスチャンがいたのです。それに対して、イエス様こそ必要かつ十分なる御方であるということを聖書は語っているわけです。
今日も、イエス様を必要かつ十分なる御方と認めきれない人たちというのがいると思います。イエス様が以外の必要はないという意味ではありませんが、イエス様が常に必要な第一であるということ、それが大事なのです。イエス様が一番であるということ、これをわたしたちの信仰とし、この一週間もイエス様と共に歩む者でありたいと願います。
|
|
 |
| 目次 |
|

|
|
| 聖書 新共同訳: |
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible
Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|