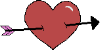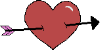|
|
|
|
前回は、律法のお話しをいたしました。律法は、神様のお言葉ですから、その一つ一つの戒めの中に、神様のご性質やお心が刻まれています。ですから、イエス様は、この律法を書き記した文字の一点一画もおろそかにしてはされてはならないとおっしゃっているのです。しかし、イエス様は当時の律法主義者たちと厳しく対立します。イエス様の目には、律法主義者たちの律法の守り方は、律法を大切にしているのではなく、それを軽んじているようにしか見えなかったのです。
律法を守るということは、その言葉の中に示されている神様の「お心」を大事にすることです。これが、イエス様のお教えになったことでした。律法の意味や価値をはき違えた人たちが、律法主義者でした。
律法主義者たちが守ろうとしたのは、「言葉」であって「お心」ではありません。律法にこう書いてあるから、これはしてはいけない。これはしてもよい。微に入り細に入りそういう律法の命令を文字通りに行うことを大切にしました。しかし、そういうことに終始するあまり、その律法が映し出している神様の姿、お心を忘れてしまっていたのです。安息日には仕事を休まなければいけないから、病人を治すことはできない。これは神様のお心でしょうか? イエス様は、安息日を定め給う神様のお心は、安息日に神様の喜ぶことを行うことだと教えられました。そして、安息日には医療行為をしてはいけないと主張する律法主義者たちの目の前で、病める人をお癒しになったのです。
それならば、ということで、姦淫の罪を犯した女性が、律法主義者たちによってイエス様のもとに連れてこられました。彼らは「律法にはこういうふしだらな女は石で打ち殺せとありますが、どうしたらよいでしょうか」と問います。イエス様は「あなたがたの中で罪のない者がこの女に石を投げなさい」とお答えになりました。これには、律法学者たちは押し黙るほかありません。律法は、罪人を裁くためのものではない。みんなが神様のお心の前で、自分の罪を知り、神様に対しても、人に対しても、謙遜になるためのものだと、イエス様は教えておられたのです。
そういうことを、『ヘブライ人への手紙』は、《律法には、やがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません》(10章1節)と言っているのです。律法の実体とは、神様のご性質やお心です。その神様のご性質やお心を映す影が律法なのです。「ああしてはいけない。こうしてはいけない。あれをしなさい。これをしない」という律法を、そのまま守ればいいというのではなく、そのように語り給う神様のお心を知ることこそが、律法を大切にすることだというのです。
ですから、イエス様は、ある意味では律法学者たちよりも厳しく律法をお語りになります。特に「山上の垂訓」と言われるイエス様の説教の中では、律法を守るといことはこういうことですと、具体的な律法を取り上げながら語られています。ひとつ、有名なところをご紹介しましょう。
あなたがたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と命じられている。しかし、わたしは言っておく。悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。(『マタイによる福音書』5章38-39節)
《目には目を、歯には歯を》とは、目をえぐりとられたら相手の目をえぐりとることができる、歯をへし折られたら相手の歯をへし折ることができる、という復讐法です。《目には目を》とは、残忍な言葉に聞こえるかもしれません。そのようなことを命じ給う神様は、たいへん恐ろしい神様に思えるかも知れません。しかし、イエス様はそうではないのだとおっしゃっています。目をえぐり取られた人は、相手の命まで取ってやりたいという激しい憎悪にかられるのが普通です。しかし、この律法は、そんな風に人を恨み、憎み、怒りの感情にまかせて相手に復讐することを禁じているのです。だから、イエス様は「悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。」、これがこの律法の精神だといっておられるわけです。
|
|
|
|
|
|
では、なぜ神様は最初からそういう仰らないのでしょうか? 最初から「目には目を」などと言わず、「悪人に手向かうな」とはっきり言えばよかったのではないでしょうか? そうではありません。なぜ、神様は「目には目を」とおっしゃったのか、そのことを深く考えることによって、この律法がどのような神様の姿を、そのお心を、映し出しているのかということがはっきりと分かってくるのです。
結論から申しますと、それは憐れみの神です。憐れみには、そこに深い痛みがあります。殴られても痛くない。裏切られて、罵られても何も感じない。そういう神様であるならば、罪人をゆるすかもしれませんが、それは憐れみではありません。罪を罪として感じないだけの話なのです。
短歌の本を読んでおりましたら、こういう歌が紹介されていました。
赦せよと請うなかれ赦すとはひまわりの花の枯れるさびしさ
松実啓子
たぶん恋人同士が喧嘩をしたのでありましょう。男が女に「ゆるしてくれ」と謝るのです。しかし、女はゆるせない。なぜか? たぶんこの男は恋人の愛を裏切ったのです。女はそれを絶対にゆるせないと言い、自分にも決してゆるしてはならないと言い含めているのです。それは、恋人の浮気を「はいわかったわ。もう二度としないでね」とゆるしてしまったら、信じ合ってきた何かが、愛し合ってきた何かが、そこでプツンと終わってしまうような気がするからです。「ひまわりの花の枯れるさびしさ」というのは、そういう気持を言い表している言葉でありましょう。
裏切った恋人をゆるさないのは、愛していないことではありません。むしろ純粋に愛しているからこそ、その信じ合う関係の中に、愛し合う関係の中に、「諦め」とか「限界」のような不純物が入り込むのをゆるしたくないのです。裏切られてしまってもなお、その関係の純粋性を壊さずに愛し続けていくためには、そのことをゆるせない、ゆるしてはならないという激しい気持を保ちながら、愛し続けていくほかないということなのです。それは、簡単にあきらめて、忘れて、その関係を持続させていくことよりも、ずっとずっとエネルギーを必要とすることです。そう考えますと、ゆるさないということの中に、愛の深さ、純粋さを見ることができるのです。
神様も、人間の罪を簡単にゆるせるような御方だったら、ずっと楽だったにちがいありません。しかし、《わたしは熱情の神である》(出エジプト記20章)と仰っておられます。文語訳では「嫉む神」です。愛の裏切りを決してゆるせない神様なのです。それほど純粋な愛をもって、私たちを愛し、求めておられるのです。だからこそ、罪を憎む気持は人一倍強いはずです。人間の罪を、愛の裏切りを、激しく憎み、その痛みを忘れようにも忘れられない神なのです。しかし、それならば人間を見捨てられるのかと言えば、それもできない。そのような神様の苦悩を表す言葉が、「憐れみ」という言葉なのです。
『ホセア書』11章は以前にもお話ししたことがありますが、何度お話ししてもいい大切なところです。1〜4節には、神様がどんなにイスラエルの民を慈しみ、深く愛してきたというが書かれています。5〜7節には、その神様の愛を裏切ったイスラエルに対して、抑えがたい怒りの炎が神様のうちに燃え盛っていることが記されています。しかし、それは神様のイスラエルに対する激しい愛のあらわれでもあるわけです。ですから、8〜9節で、神様はこう仰います。
ああ、エフライムよ
お前を見捨てることができようか。
イスラエルよ
お前を引き渡すことができようか。
アドマのようにお前を見捨て
ツェボイムのようにすることができようか。
わたしは激しく心を動かされ
憐れみに胸を焼かれる。
わたしは、もはや怒りに燃えることなく
エフライムを再び滅ぼすことはしない。
わたしは神であり、人間ではない。
お前たちのうちにあって聖なる者。
怒りをもって臨みはしない。
どんなに愛を裏切られ、傷つき、哀しみ、怒りの炎が燃えさかっても、まだ「ああ、お前を見捨てることができようか。お前を引き渡すことができようか」と、イスラエルに対する深い愛を隠すことができない神様の葛藤、それが激しい言葉でここに吐露されているのです。
わたしは激しく心を動かされ
憐れみに胸を焼かれる。
わたしは、もはや怒りに燃えることなく
エフライムを再び滅ぼすことはしない。
ここに《憐れみに胸を焼かれる》という言葉が出て来ます。これは神様の感情を表しているのです。神様は「真理」、「光」、「永遠」と言われますが、同時に神様は「命」なる御方であることを、忘れてはいけません。命とは、私たちの命を考えてもわかりますが、理屈ぬきに悲しんだり、苦しんだり、震えたり、弱ったり、いつもぐらぐらと揺れ動きます。この命こそが神様の愛の根源なのです。
理性的に考えたら、罪人は罪の報いをうけるべきです。愛を裏切ったものは、その報いをうけるべきです。それが道理であり、正義というものでありましょう。けれども、そういう道理とか、正義とか、真理をお持ちの神様が、理屈抜きで罪人が罪のゆえに亡ぼされていくことに耐え難い哀しみを感じ、「ああ、やっぱりお前を見捨てられない」と、神様が叫びます。それが「憐れみ」です。
このような神様の非の打ち所のない純粋な愛を裏切ってしまった愚かで、惨めな人間は、神様の正義、真理、法の前では、まったく立つ瀬がありません。しかし、神様の中にお前が罪を犯そうが、裏切ろうが、何をしようが、見捨てられない、愛し続けたいという、胸を焼かれるような憐れみの情が起してくださる。罪を犯した人間にとって、愛される資格を失った人間にとって、それが唯一の望みとなり、拠り処になるのです。
神様は人間を愛するがゆえに、その愛の裏切りを憎み、罪をゆるせない神様です。みなさんも、見も知らぬ人に殴られるよりも、愛して信頼して人に殴られた方がずっと痛いにちがいありません。ずっとゆるせない気持にかられるに違いありません。神様もそういう御方です。しかし、同時に取り返しのつかない罪を犯しておろおろするばかりの人間を見ると、無条件に「お前を見捨てられない」という憐れみの情に魂をゆさぶられる御方なのです。一方では罪に対する激しい憎しみを持ちながら、他方では罪人に対する深い憐れみをもたれる。その罪への憎しみと痛みと、罪人に対する憐れみが、神様に《目には目を、歯には歯を》と言わしめるのであります。罪は憎むべきものだ。しかし、その罪に対する憎しみをもって罪人を裁いてはいけない。罪人を憐れみなさいということです。
その神様のお心がわかるならば、《目には目を、歯には歯を》という言葉を聞いたときに、「やられたらやりかえそう」なんて事は思い浮かばないはずだと、イエス様はおっしゃるのです。神様のお心を考えたならば、罪を憎み、罪をゆるしがたいと思いつつも、憐れみなさいということなのです。 |
|
|
|
|
|
さて、今日お読みしました『ヘブライ人への手紙』10章5-7節、これは詩篇40編からの引用です。この詩篇はダビデの作となっておりますが、『ヘブライ人への手紙』は、イエス様の言葉だと説明しています。おかしいじゃないかと思われるかも知れませんが、おそらくイエス様が、この詩篇を弟子たちに聞かせて、これは私のことを書いているのだよと仰ったのではないでしょうか。これはわたしの想像にすぎませんが、いずれにせよ、ここにはイエス様が御自分のご使命についてどのように語っておられたのかということが書かれているのであります。それは、御自分の体を、人間の罪をつぐなう神への捧げ物として捧げるためであったということです。
今日から、教会もクリスマスの装いをいたしまして、イエス様のご降誕をお祝いする季節に入りました。クリスマスは、イエス様の誕生祭でありますからめでたきことに違いありませんが、イエス様はその神様から与えられた体を十字架に捧げるために、私たちの世にいらしてくださったのだということを考えますと、少なくとも教会のクリスマスは、ただうれしい、たのしいというだけのクリスマスであってはならないと思うのです。
罪を憎む神様が、罪人を見捨てることができない深い愛をもって、罪人の救いのために、御自分のひとり子なるイエス様を十字架につけるためにお送り下さいました。十字架は、先ほどホセア書をとおしてお話しをしましたように神の憐れみ、神の義と愛の葛藤がある場所です。神様が罪を憎んでいなければ十字架はありませんでした。神様が罪人を愛する方でなければ十字架はありませんでした。十字架には、私たちの罪のゆえに悩まれる神様の苦しみがあるのです。そして、その十字架がなければ、私たちの喜びであるクリスマスもなかったのです。
この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が献げられたことにより、わたしたちは聖なる者とされたのです。(10節)
《この御心》といわれているのが、御自分の胸を焦がし、はらわたを揺り動かされるような思いをして、罪人を救わんとする神様の憐れみです。この憐れみによって、イエスさまがお生まれになり、十字架にかかられたのです。神の痛み、神の苦しみである十字架があればこそ、私たちの喜びであるクリスマスもあるのだということは、私たちは決して忘れて過ごしてはなりません。 。
|
|
 |
| 目次 |
|

|
|
| 聖書 新共同訳: |
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible
Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988
|
|
|